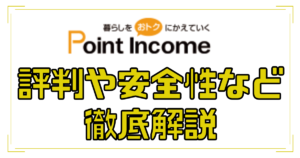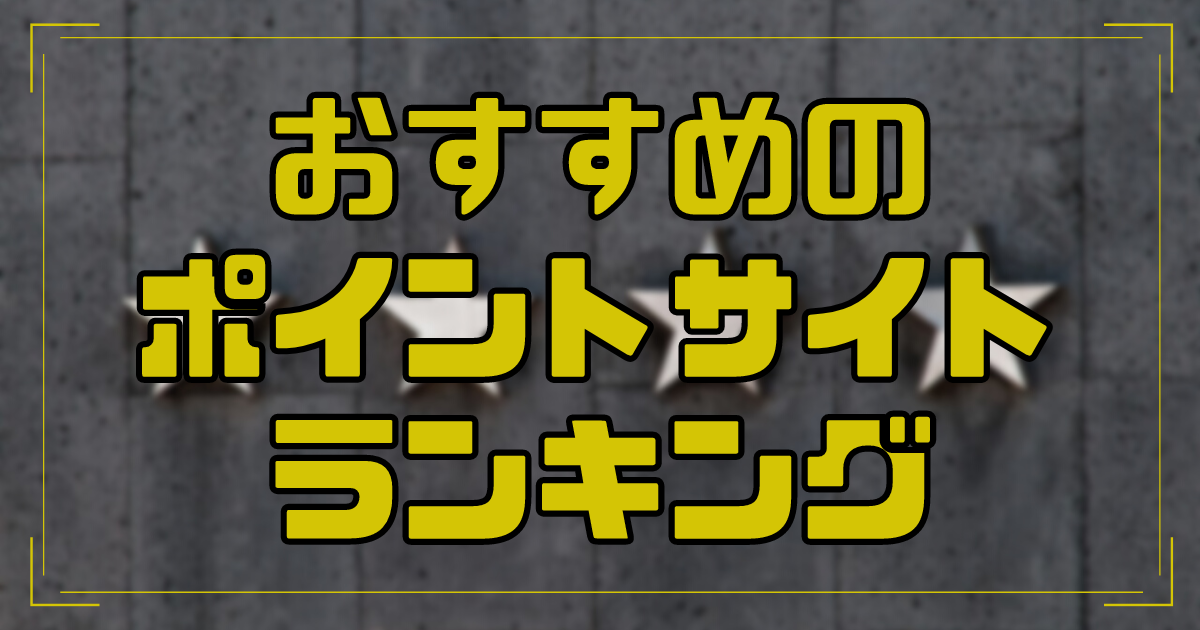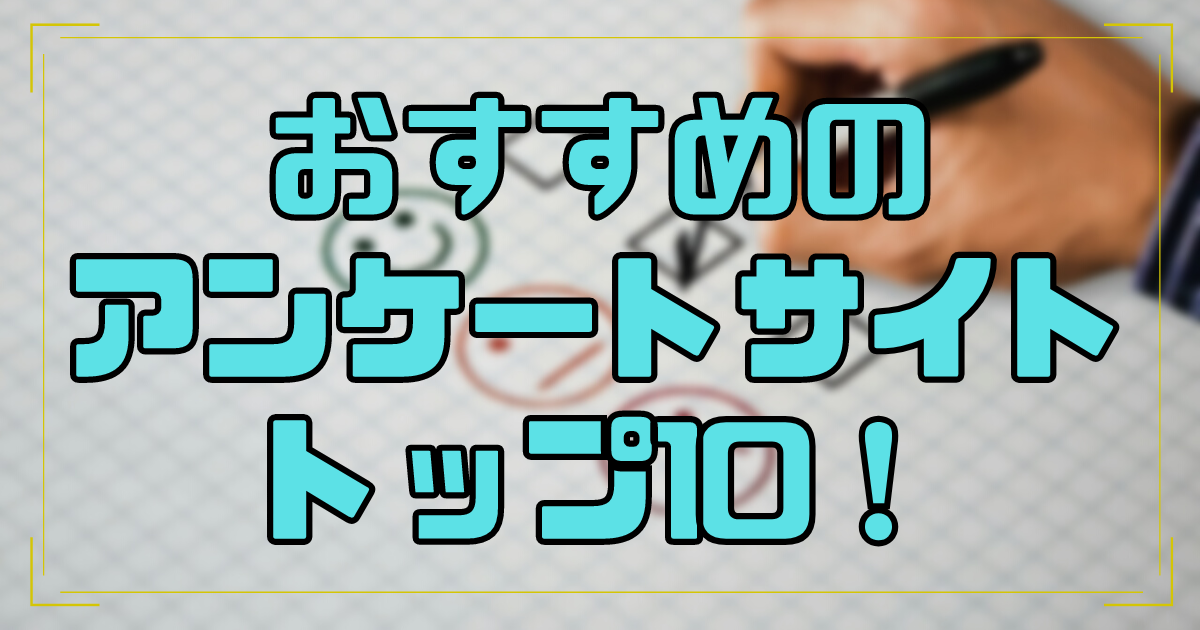勉強をもっと楽しくできたら捗るのに。ゲーム化すれば本当にゲームのように勉強できるようになるの?
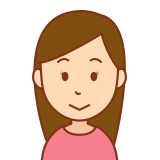
勉強のゲーム化の方法を具体的にどうすればいいのか知りたい。
今回はこういった悩みを解消します。
✅内容は
1、ゲームが楽しいと感じるカラクリ
2、勉強とゲームの共通点&相違点
3、勉強をゲーム化する具体的な6つの方法
4、勉強を自分なりにゲーム化する時のポイント
近年はゲームを仕事や勉強に応用するというゲーミフィケーションという動きがあります。
今回はそのゲーミフィケーションをもとに勉強をゲーム化して楽しく勉強する方法を紹介します。
それと共にみなさんが自分で勉強をゲーム化できるためのアドバイスもしていこうと思います。
ぜひ参考にしてください。
ただし休憩中に本当のゲームをするのはあまり良くないかもしれませんよ。
勉強の休憩中にゲームはあまりお勧めしない理由。脳は休まらないから
目次
・ゲームが楽しいと感じるカラクリ

では最初になぜゲームが楽しいのかを理解していきましょう。
知っておくことで勉強に生かしやすくなります。
細かく説明すると個人の感覚にもよりますし、何よりキリがないのでここでは大まかに3つご紹介します。
1、成長が目に見えてわかるから
2、何をすればいいのかわかりやすいから
3、実際にプレイしながら覚えていくから
ではそれぞれ説明していきます。
1、成長が目に見えてわかるから

正直これが一番肝となるものです。
ゲームだと例えばモンスターのレベルが上がるとか、強いキャラクターを手に入れるとかです。
さらに発展してそれらのおかげでさらに強い敵を倒せるようになったり、行けなかったところに行けるようになったりです。
こんな風にどんどん自分が成長してるのが一目瞭然となります。
これが楽しいという人が多いのではないでしょうか。
もちろんストーリーとかもありますが、ポケモンなどではこの傾向が強い気がします。

僕はひたすら育てるのが好きで意味もなくレベル100のポケモンをいっぱい作ってました。
でもそれも今思えばポケモンが成長してるのがレベルという数字で分かるのと、新しい技を覚えたり進化したりとハッキリ目に見えるからですね。
2、何をすればいいのかわかりやすいから
これは例えば今のスマホゲームで言うと、ミッションというどう進めればいいかの方針があります。

それだけでなくデイリーミッションとかマンスリーミッションなども用意されていますね。
これらのおかげで次何をすべきか迷わないですし、達成したら報酬がもらえるというご褒美も待っています。
何をやるかが明確なおかげでこの達成感が得られるのが強いです。
スマホゲームじゃなくてもポケモンでも次の街のジムリーダーを倒して、最後には四天王を倒してという流れがあります。

僕はポケモンっ子だったので、ポケモンばかりですみません。ドラクエなどもボスを倒すなど同じはずです。
スマホじゃない場合はラスボスがいて、そこまでに中ボスがいたりとか、段階を経て目指すことが多い気がします。
3、実際にプレイしながら覚えていく

これはゲームをしてると当たり前に感じると思いますが、勉強と大きく違うところなので覚えておいてください。
ゲームだといきなりこのシステムはこうで、こういう風に相手を倒してと言うチュートリアルが、言葉だけで説明されることはないはずです。
実際にプレイしながら覚えていくと思います。
またチュートリアルも出来るだけ簡潔にされており、難しい内容はまたレベルが上がったら徐々に説明されていくスタイルが多いです。
このプレイをしながらレベルに合わせて新しいことを覚えていくというのは楽しむ上でとても大切です。
いきなりわからないことをたくさん説明されても、覚えれなくてうんざりしてしまうでしょう。
・勉強とゲームの共通点&相違点

では本題の勉強の話に入っていきますが、勉強とゲームがどう似ていてどこが違うのか話していきます。
✔️共通点
共通点は「実際に受験というラスボスがいて、それに向けて自分を成長させていくという点です。」
ポケモンでもレベルを上げて強くすることで、四天王に勝つことを目指しますよね。
それと同じで勉強でも受験という最終ボスがいたり、受験じゃなくても試験というラスボスがいるはずです。
そしてその過程では模試という中ボスがいるはずです。
なので勉強は土台自体はゲームと同じなので、大いに楽しめる可能性があるのです。
✔️相違点
ではなぜ勉強はゲームと違って楽しめないのかということが相違点で明らかになります。
相違点は2つあります。
1、運などもあり成長が目に見えないづらい
2、何をすればいいかの指針が不明瞭
一つ目に関しては確かに模試という力を試す場はありますが、それはゲームのように自分の好きなタイミングでできるものではありません。
そして回数も少なめです。
また受けたとしても試験の場合多少の運も関わってくるため、ハッキリと実力が目に見えません。
また二つ目に関してが一番大きいのですが、勉強の方法に正解はありません。
確かにネットで調べれば合格するためにこういう勉強すればいいよ、とかは書いてます。
しかしそれはその人に合っていたからなだけだったりしますし、それに大まかな方法は書いててもより細かな指針はありません。
それは自分で決めないといけないのです。
この2つのせいで勉強は土台はゲームと一緒でも楽しめなくなります。
ちなみに勉強を根本から楽しむ方法についてはこちらをどうぞ
勉強の楽しい要素とは?[結論]続けないことにはどんなことも楽しくない
・勉強をゲーム化する具体的な6つの方法

ではここまでのことを踏まえてどうすればいいのか具体的に6つの方法を紹介します。
ゲームと違うのならば、勉強をゲームのシステムに当てはめていけばいいだけの話です。

自分なりのスタディという名のポケモンゲームを作ってみましょう。
6つもあるので1つずつ試して自分にあってると思ったものを取り入れてください。
1、問題集や大学の過去問をボスに見立てる
2、自分の能力を視覚化する(ステータスみたいに)
3、問題集や参考書にレベルをつける
4、チェックリストを作る(デイリーミッションみたいに)
5、友達と同じ問題を解いて競う
6、友達と集まって同じ問題を協力して解く
これだけではよくわからないと思うので、それぞれ解説していきます。
1、問題集や大学の過去問をボスに見立てる
まずこれはそのままの意味で、ゲームにおけるボスというのを勉強でも作ろうという事です。

受験が大ボスじゃないかと思うかもしれませんが、受験では遠すぎます。模試も自分でタイミングを決められなかったりと融通が効きにくいため過去問にするのです。
ではなぜそれが良いのかというと、ゲームを想像してみてください。
ゲームでは序盤はそこまで詰まる事なく、ストーリーを進めることができると思います。
しかし中盤あたりになってくるとそう簡単には進めず、相手に負けたりして一回挫折を味わいます。
そこでその相手に勝つために、少し弱いところでレベル上げをして、やっと勝てたときにはすごい達成感だと思います。
その効果を勉強でも狙うのです。
大学の過去問や難し目の問題集を解くことがボスを倒すことだとすると、そのために自分のレベルを上げないといけません。
そうやって苦労して解くことで達成感と同時に自分が育ってるという感覚を得ることができます。
一つだけ注意が必要なのは、難しすぎる問題をボスにしてしまうと、ゲームで言うラスボスがいきなり来てる感じで、一瞬で心が折れてしまいます。
なので難易度はうまく調節してください。
だいたい1週間から1ヶ月くらいレベル上げをしたら、倒せるぐらいのボスにしましょう。
2、自分の能力を視覚化する(ステータス)
これはゲームで言うと、ステータスにあたる攻撃とか防御とかみたいに自分の実力を数値で表してしまおうというものです。
これは先ほどのボスに見立てるという方法と併用すると強力です。
なぜかというと、自分の能力を視覚化することで、今日のレベル上げでどれくらい強くなったとかわかるからやりがいがあるものです。

ボスに挑む前のレベル上げの時に、自分の能力が育ってるのが目に見えてわかると、さらにレベル上げのやりがいが出てきます。
そういう意味でボスに見立てる方法と併用するのが効果的なのです。
✔️方法
この数値化の方法は、最初の値は模試の点数から考えて、それ以降は毎日か1週間に一回どんなことをやって、どれくらいの力がついたか分析していきます。
今日は日本史で一つの時代を一通り勉強して3割ぐらいは覚えれたから、日本史というステータスは+3とかそんな感じです。
またもっと面白くするなら、全てのステータスを総合的にみて、自分のレベルというのもつけると良いでしょう。

僕はポケモンが大好きだったので、最大レベルは100にして各ステータスが10上がったらレベルが1上がるとかにすると面白いです。
一つだけ注意すべきことは、どうなったらステータスが上がるとか、レベルが上がるとかの基準はある程度は決めておきましょう。
数学ならチャートの問題が3つ解けるようなったのなら数学というステータスが1上がる、という風に事前に決めておくのです。

そうしないと毎回考えていては疲れてきますし、そこに無駄に時間とエネルギーを使ってしまいます。
3、参考書や問題集にレベルをつける
先ほどの自分の能力を視覚化するというのは、自分が戦う側になってるわけです。
しかしこの参考書や問題集にレベルをつけるのは、自分は参考書というキャラを扱って相手と戦うという感じです。
例えば、英語のネクステで右ページの問題の正答率が5割ならレベルは100をマックスにして50とかです。

もし正答率が7割に上がればこのネクステは今レベル70だ!と思います
そして勉強して正答率が上がったらレベルも上がるという感じで、それを自分が使ってる問題集などに個々に付けていくのです。
僕は先ほども言ったようにポケモンが好きだったので、どっちかというとこちらの方が楽しいです。
様々なキャラを育てていく感じがして、RPG的で楽しく感じます。
ただこれも注意が必要なのはレベルの基準を正答率という風にある程度決めておくことです。
4、チェックリストを作る(ミッション)
だいたいのゲームには大筋のストーリー以外にも、サブミッション的な要素がありそれを達成すると、経験値がもらえるとか、アイテムがもらえると思います。
勉強では大筋は1の過去問を倒すことだとすれば、ここではそのサブミッション的なものを設定する方法を紹介します。
サブミッションは特にアプリのゲームとかだとデイリーミッションとかウィークリーミッション、そして普通のミッションとかがあると思います。
もし余裕がある人はそれぞれ設定してノートとかに書いておくと相当面白いと思います。
しかしそこまで時間はかけずともデイリーミッションだけでも設定しておくと、効果は大きいですし、楽しいと思います。
デイリーミッションとは要するに1日のタスクのことで、英単語帳を30ページ進むとか、チャート5問解くとかです。
ウィークリーになってくるともっとページ数や問題数は増やして、普通のミッションだと一つの問題集とかになってきます。
これらは必ずノートに書いて、達成できたらチェックをつけます。
アプリのゲームではデイリーやウィークリーは全て達成できたら一つの報酬がもらえるという感じです。
なので勉強でも同じように全てクリアできたら何か報酬をもらえるようにあらかじめ設定しておきましょう。

これが超重要なので絶対覚えておいてください。
原液のカルピスを買っておいて、クリアしたら夜に一杯作って飲んで良いとかです。
ただこのサブミッションはあくまでも大筋のものではないので、大筋の過去問を倒すということの手助けとなりつつ、邪魔にもならないくらいの量にしておきましょう。
普通のミッションとなると、大筋のストーリーに関わってくるものが多いのでそこは同じように重要なものをミッションとして良いでしょう。
5、友達と同じ問題を解いて競う
これはアプリのゲームによくある、ランキングみたいなものです。
友達と示し合わせて同じ問題を解いて、どっちの方が点数が高くかつ、早く解けたかなどを勝負しましょう。
こうすることでその時に集中して問題を解くことで自分の力になるだけでなく、友達たちの中でランキング1位を取るために勉強しようとなるでしょう。

ゲームでもランキングで上位になるために強くするということはあると思います。
そしてこれも先ほどと同じように報酬をつけても面白いと思います。
ただしこれは友達も関わってるので、そこを加味して1位の人には一日敬語で喋らないといけないとか、最下位の人が1位の人に飲み物を奢るとかです。
ただ頻繁に行うなら出来るだけお金関係は避けたほうがいいでしょう。
そして注意が必要なのは、あまりに強すぎる人や弱すぎる人がいると面白くないということです。
ゲームではそう言うことが起こらないように、レートというのが設定してあって、だいたい同じくらいのレートの人が当たるようになってると思います。
そうやって勝負する人は多少は選びましょう。
6、友達と集まって同じ問題を協力して解く
これはゲームで言うとマッチングして一緒に戦うみたいな感じです。
ただし1人で簡単に解けてしまうようなものでは面白くないので、若干難しいぐらいの問題を解いてみましょう。
自分が目指す大学の少し下ぐらいの問題とかを使うといいと思います。
例えば日本史のどっかの私立の問題を持ってきて、みんなでここはこれだとか議論しながら進めていきます。
そうすると1人で知識を入れるのとは違い新たな発見があったりしますし、友達となので楽しいです。
国語とかは難しいかもしれませんが、一つの問題ごとに時間をとって、ある程度解いたらここはこういう風だとか議論していくといいでしょう。
数学でもここであの公式を使うんじゃないとか言い合うのは結構楽しいです。
ここでは逆に1人ずば抜けて賢い人がいても面白いと思います。
・勉強を自分なりにゲーム化するときのポイント

ここまででおすすめのゲーム化の方法は紹介しましたが、じゃあ一体これらの方法は何に基づいて考えたのかを説明します。
そうすることでみなさんが独自にゲーム化をできるようにしていきたいと思います。
最初にすることとしてはまず自分が今もしくは以前好きだったゲームを思い出してみてください。

僕はポケモンとモンストとウイイレです。
そしてあるポイントに沿ってそのゲームの要素を勉強に移していくのです。
そのポイントは3つ。
1、報酬系
2、達成感
3、ワクワク感
4、闘争心
この3つに目をつけることで、勉強をゲーム化していくことができます。
もちろん感情は人それぞれなので、ゲーム化する過程でこれら以外のこの感情は使えると思ったらしっかりメモして、うまく利用していってください。
それぞれ簡単に解説していきます。
1、報酬系
やはりゲームではなんと言っても、何かを成し遂げた時の報酬というのは大切です。
報酬がないのに、サブミッションとかがあってもやらないと思います。
ですから勉強に限らず何かをやる時には報酬というのは重要です。
なので自分の好きなゲームでは何をすると報酬をもらえたかなーというのを思い出し、それを勉強に応用してください。
ですが一つだけ危ないのは、全てに報酬をつけていると、見返りがないと何もやらない人になってしまいます。
それは勉強などではそれでいいかもしれませんが、人間関係とか友達相手にもそうなってしまうと仲が途切れてしまったりするので注意しましょう。
2、達成感
これはある一つのステージをクリアした時などやレベルを最大まで上げた時の達成感です。
勉強でも達成感があるとまた次も頑張ろうと、次につながるので必要です。

例えば僕はポケモンのレベルを100にするのが達成感があって好きだったので、参考書にレベルをつける方法を考えました。
ですから達成感というものにも目をつけましょう。
4、闘争心
これはあいつにだけは負けたくないとか、出来るだけ上に立ってたいというような思いがあると思います。
それはゲームでも勉強でも同じで、対戦する時に負けたくないとか、負けて一切悔しくないことは滅多にないでしょう。
ですから闘争心というものにも目をつけます。
そこから友達と同じ問題を解いてきそうという方法を考え出しました。
こうやってゲーム化をするときはこれらの感情の動きから勉強に活かせる場所を見つけるといいでしょう。
・まとめ:ゲーム化は最強の勉強法と言っても過言ではない

今回の内容をまとめていきます。
6つの具体的方法をもう一度ご紹介するので覚えて帰ってください。
1、問題集や大学の過去問をボスに見立てる
2、自分の能力を視覚化する(ステータスみたいに)
3、問題集や参考書にレベルをつける
4、チェックリストを作る(デイリーミッションみたいに)
5、友達と同じ問題を解いて競う
6、友達と集まって同じ問題を協力して解く
この6つでしたね。
全部が全部実践しようとするのではなく、少し試してみて自分に合うと思ったものだけ行うようにしましょう。
無理をしてしまうと逆に勉強が捗らずに無意味になってしまうので。
勉強を本当にゲーム並みに楽しくできたら正直最強です。
ぜひ皆さん試してみてください。
最後まで閲覧ありがとうございました。