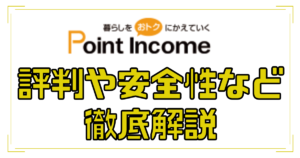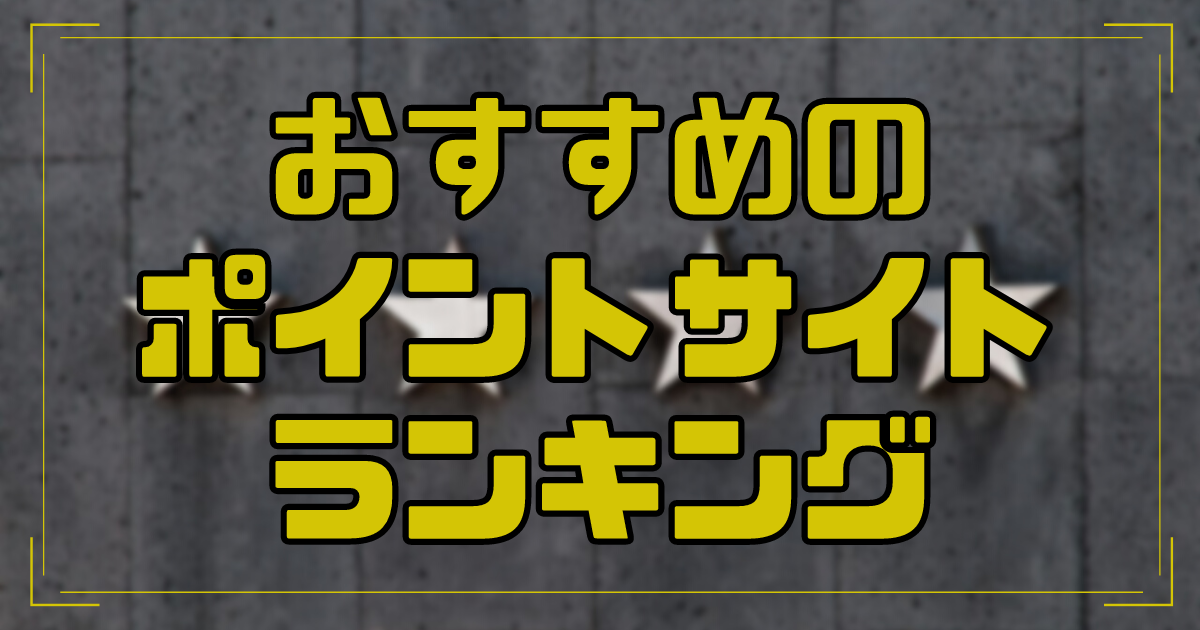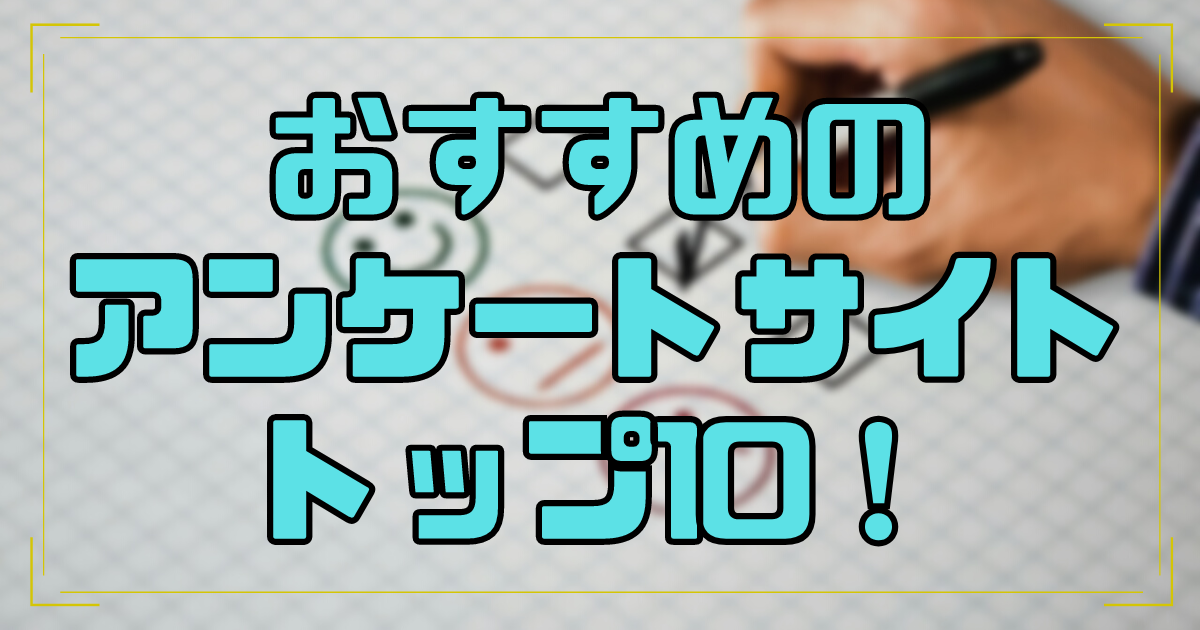大学受験の数学って参考書って数限られてるけど普通に学校で配られたやつでいいの?
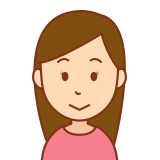
阪大の数学レベルだとどれくらいの参考書を使わないとダメ?

どの学校を目指すにも必須の参考書とかあるの?
今回はこういった悩みを解消します。
✅内容は
1、数学の参考書選びのポイント
2、阪大生が勧める文系数学の参考書
3、数学の参考書を使う時の注意点
今回は僕が実際に現役の頃に使っていた参考書、問題集たちを紹介したいと思います。
ここでは僕が実際に使ったものしか紹介しないので、他のものも知りたい時は他のサイトを参考にしてください。
というのも世間でいいと言われてるものたち全てを紹介しても見てる方はややこしくなるだけだと思うので。
今回はこれだけやれば阪大には多少余裕を持って受かることができるという基準になるかなと思います。
目次
・数学の参考書選びのポイント

数学における参考書選びのポイントは一つだけです。
それは段階的にということです。
これは英語の参考書の時にも言いましたが数学の場合は特にです。
数学はやはり基礎的な問題と発展的な問題の差は大きいからです。
三次関数の問題で三角関数が出てきたらこれは複合問題で微積と三角関数の両方ができていないと解けなくなります。
こういう風にそれぞれの基礎ができて初めて次のレベルの問題にとりかかれるという風になっています。
ですから数学においては基礎がとても大事でいきなり難しい問題に取り掛かろうとしないでください。
・阪大生が勧める文系数学の参考書!

1、教科書
・おすすめ度:*****
・デメリット:実践は不十分
・メリット:解説が分かりやすい
必ずみんな持ってる
基礎知識はこれで完璧
・解説

まず最初に紹介するのは教科書しかないです。
教科書は学校で使うので必ずみんな持っていると思いますが意外と参考書を探してる方の盲点となっているのではないでしょうか。
やはり授業で使うものとして位置付けられているため自分で勉強する時に使おうとは思わなかったりします。

しかし教科書はおそらくほとんどの高校で使われるのではないでしょうか。
ということは高校生なら誰でも理解できるように作らないといけないはずで、ですから解説はどんな参考書よりも分かりやすく書いています。
それに基本事項はおおよそカバーされているため教科書さえ抑えておけば次のステップに進めるわけです。

僕は受験の数ヶ月前も教科書に載ってることで抜けてることはないか確認するほどでした。
ただ一つ注意が必要なのは基本知識はおおよそカバーできますが、その知識の運用はまだ教科書では不十分だということです。
ですからそこはつぎに紹介するチャートで補うわけです。
2、青チャート
・おすすめ度:****
・デメリット:量が多い
・メリット:網羅的
演習を大量に積める
・解説
まずデメリットの話からすると、やはり量が多いというのが難点でしょう。

青チャートをやろうと思って一番困るのがこれだけの量、しかも1周じゃ意味がなく何周かしないといけないと考えるとゾッとするでしょう。
しかしその分網羅的であるということが言えます。
基本的な問題から結構難しい問題まで幅広く載っています。
ですから自分の目指すレベルに合わせて問題をある程度取捨選択していく、また下に付いている練習問題はやらず、基本問題だけやればある程度時間は短縮可能です。

実際僕もこれは流石にできなくていいだろうというのが数問ありましたし、練習問題は一問も解きませんでした。
そしてこの前の段階で教科書で見つけた知識を使える知識にしてくれるのがこのチャートです。
そりゃこれだけ問題があれば嫌でも使える知識になるのでそこは安心してください。
確かにチャートは問題が多く大変と言いましたがチャート2冊で阪大ぐらいの数学なら事足りると思うので、チャートだけで大学受験の数学が身につくなら結構簡単かなと思います。
他の参考書を何冊かやるのはどれがいいか調べるのも大変ですし、この2冊で済ませれば楽なのでお勧めします。
青チャートの効果的な使い方はこちら↓
青チャートの使い方次第で旧帝大の数学も解ける。コツは繰り返しとランダム!
詳しい数学の勉強の仕方はこちら↓
3、数学良問プラチカ
・おすすめ度:***
・デメリット:とても難しい
・メリット:高難度の応用力身につく
考えても中々解けない問題に対する対処法が身につく
・解説
僕はチャートまでで十分と言いましたが、時間があったためプラチカにも手を出しました。

結果的にプラチカを極めるほどはやりませんでしたが、2周ほどはしました。
プラチカはとても難しいです。
京大、東大の問題はもちろん載ってますし、一橋などの難しいところも載っています。
ですから京大、東大を目指す人か、もしくはもうある程度数学に自信があって時間的にも余裕のある人がやるべきです。
正直1周目では解けない問題が多かったので、解けない問題に当たった時の対処法を身につけることができました。

またそこで三角関数を使うのかやなど、思わぬところで公式を利用する面白い問題がたくさん載っているため応用力が身につきました。
しかしやはり高難易度だったため必ずやるべきだったかと言われると、僕にとってはそうではありませんでした。
実際プラチカの半分以上の問題は、阪大の文系数学では出ないようなレベルだったのであまりできても意味ないといった感じでした。
ですから本当に数学の超難問が出るような大学を目指す人以外は青チャートまででいいと思います。
・数学の参考書を使う時の注意点
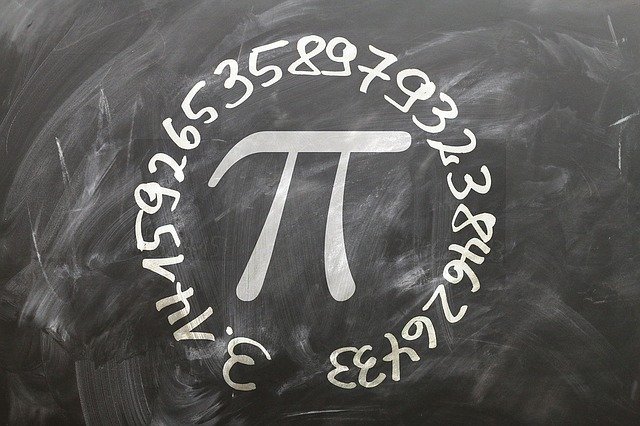
数学の問題集を使うときの注意点は2つあります。
1、1問1問じっくり考えないようにする
2、複数の問題集を同時に行わない
です。
それぞれ解説していきます。
1、1問1問じっくり考えないようにする
1つ目ですが、数学の問題集は他の英語や国語に比べ載ってる問題の量が桁違いです。
ですからじっくり考えててはいつまで経っても終わらないというのが1つ目の理由です。
特にチャートなんかは1A2B全てあわせて700〜800問ぐらいあります。
そして2つ目の理由は数学の特にチャートなどの基礎〜発展ぐらいの問題集を解くときの目的というのは、問題のパターンを覚えてしまう事です。
じっくり考えているとその場では思いつくかもしれませんが、やはり時間がかかって最初の方にやった問題ほど忘れてしまいます。
ですからパッと思いつかない問題もじっくり考えるのではなくて、答えを見てしまってそうだったと思い出すなり理解するなりが大切です。
じっくり考えるのはプラチカや大学の過去問の時に行うものです。
2、複数の参考書を同時に行わない
ここで言いたいことはあくまで同時にはダメで、問題集の途中でこれはレベルが低いから別のにしようというのは構わないということです。
ではなぜ同時はダメかというと、先ほども言ったようにチャートなどはパターンを覚える事が目的です。
ですが複数の参考書を使うと同じ分野でも問題の大体の流れは一緒だが少し違う部分もあります。
そうなってくると特にまだあまり知識がついてない時なんかは、一緒のパターンの問題だと気付けずに別々の問題として2倍の量覚える必要が出てきます。
またこっちの問題集ではこうだったのに、あっちの問題集ではちょっと違うという風にこんがらがってしまいます。
ですから同時並行で複数の問題集を進めるのはやめましょう。
・まとめ:数学は青チャートが結局最強

今回は僕が実際に使っていたという経験談に基づいて数学のおすすめの参考書、問題集を紹介させていただきました。
正直青チャートさえ極めれば多くの大学は大丈夫です。

他の参考書はどうなのと気になる方は他にまとめているサイトはいっぱいあるのでそちらを参考にしてください。
皆さんのお役に立てていたら幸いです。
閲覧ありがとうございました。
英語の参考書に関してはこちらをどうぞ。
阪大生が勧める大学受験英語におすすめの参考書。これで余裕で合格だ!