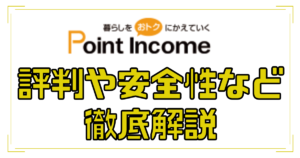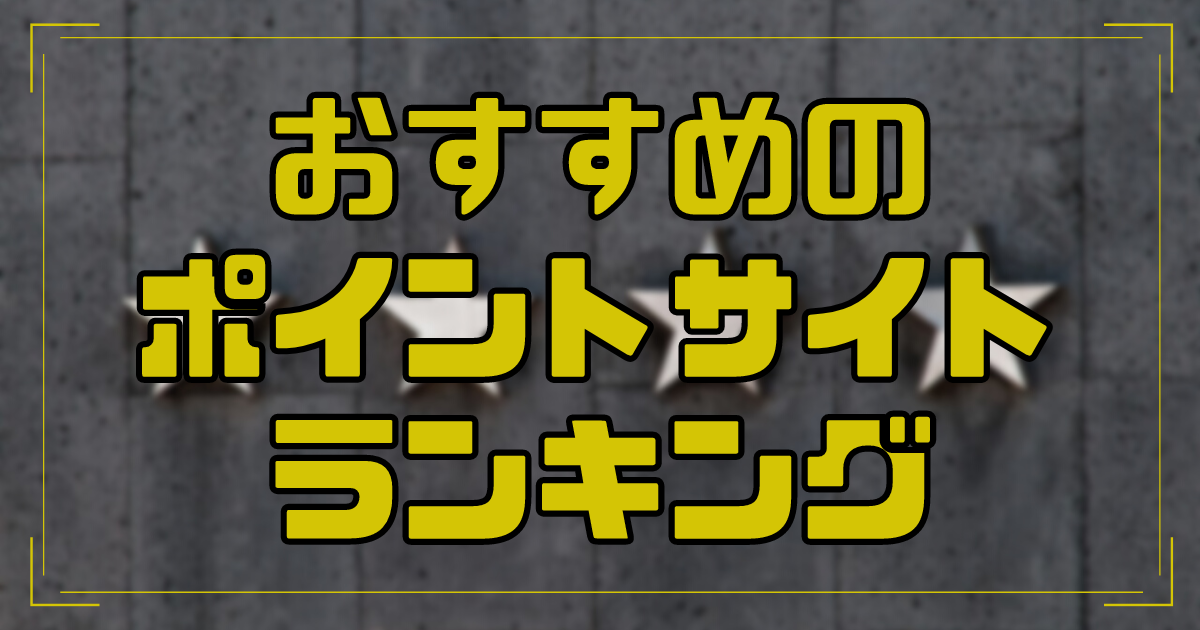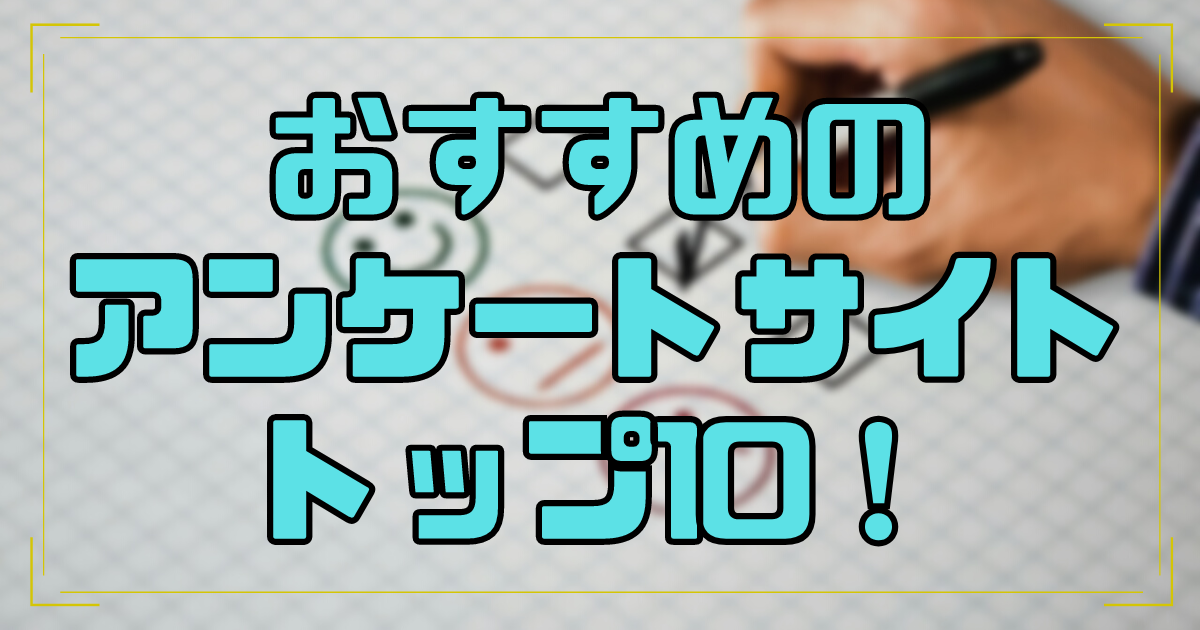この春から新しく大学生になるが、あまりSNSを使っておらず友達ができるか不安
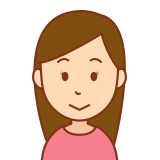
正直SNSを活用するのが面倒だが、使わないとこのご時世(コロナなど)うまく友達ができないのか実際気になる

コロナのせいで大学に行く機会がほとんどなく友達がなかなかできずSNSを使うべきか悩んでいる
今回はこういった悩みを解消します。
これから大学生になるという方中心ではありますが、コロナでオンラインばかりという事情から大学1年生の方にはだいたい当てはまる内容となっています。
✅内容は
1、大学生になってSNSで友達を作らないデメリット
2、SNSを使えばどんな効果がある?
3、どうしてもSNSを使うのが面倒な人は大学主催の交流会に参加すればOK
4、使うならTwitterで始まりからのLINE&インスタの流れが最強
5、効果的なTwitter&LINE、またインスタの使い方と注意すべきこと
6、春から〇〇大ツイートについて
です。
2021年から現役大学2年生になるので、ちょうど1年生を経験したところで具体的なことがわかります。
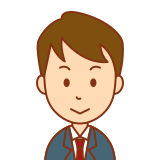
また僕はSNSをあまり使わなかったタイプなのでそれによる後悔などがよくわかります。
確かにSNSを使いませんでしたが、気の許せる友達はできたので、使うのが面倒な人向けにその場合の対処法も紹介できます。
ぜひ参考にしてください。
目次
・大学生になってSNSで友達を作らないことのデメリット

では早速大学生にもなったのにSNSで友達を作らないことのデメリットをお話しします。
実際にSNSを活発に利用しなかった僕が言うので生の体験をお届けします。
デメリットは3つです。
1、初めて同じ学部の人と会った際の壁が大きい
2、様々な交流の場を逃す
3、大学関連の情報を得るのが難しい
ではそれぞれ解説していきます。
1、初めて同じ学部の人と会った際の壁が大きい
これは例えばSNS上で多少なりとも繋がっていれば、初めて直接会った時でも

あーTwitterでフォローしてるよね
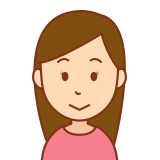
インスタで見たけど春休みにどこどこに旅行行ってたよね!いいなー
という風になります。
しかしSNSを使ってないとそういったファーストインプレッションというものが存在しません。
そのため直接会った時が本当の初めてとなり、相手のことがよくわからないので話をするきっかけがなかなか掴めなかったりします。
この場合自ら頑張って会話していかないといけないので大変だったりします。
2、様々な交流の場を逃す
これは僕が痛感したことなのですが、SNS上で友達を作っていないと学部学科のLINEグループに招待される機会もありません。
しかし春休みの間にLINEのグループで会える人で遊んだりと意外と交流の場があったりします。
もしくはzoomを使って学生たちで交流会をしてたりします。
僕はその存在すら知らなかったのでもちろん参加することもなく、交流関係を広げる上で出遅れたのは確実です。
3、大学関連の情報を得るのが難しい

大学での第一関門は初授業ではなく履修登録や様々な設定です。
実はこの最初の設定や履修登録が非常にわかりにくくとても苦労します。
例えば

一年生の間にどんな単位を取っておかないといけない
とか
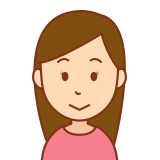
履修登録はこのページからこうやって、抽選期間はこの時期で修正期間はその後のこの時期で
などこういった詳しい情報が必要になってきます。
これが調べてもなかなか見つけずらく、見つけたとしても本当にこれがあっているのか不安になってしまいます。
この時にLINEグループなどに入っているとそこの人に質問できとても心強いです。
僕は入ってなかったので全て自分で調べてやらなければならず、結構苦労しました。
実際その後にLINEグループに入ると、みんな自分の取ってる授業に関する疑問点などを質問する場となっていました。
・SNSを使えばどんな効果がある?

では一方でSNSを使った場合にどんな効果があるのかお話ししていきたいと思います。
こちらは実際にSNSを使っていた友達を横で見ながら感じたことです。
1、これからどんな友達と付き合っていくかの選択肢が豊富になる
2、会う前からある程度の面識ができる
3、同じ趣味を持つ人と繋がり、サークル仲間にもなりやすい
ではまたそれぞれ解説していきます。
1、これからどんな友達と付き合っていくかの選択肢が豊富に
これはまさにSNSだからこそですが、同じ大学内学部でもいろんな趣味を持つ人がいます。
SNSだとそういったことはプロフィールに書いていたりするので、現実で話すよりも見つけやすいです。
ですからSNS上でいろんな人と関わりを持っておくことで実際大学内でどんな人と関わっていくか、事前に情報を知ってることで選択肢が増えます。
2、会う前からある程度の面識ができる
実際に僕が体験した例をご紹介します。
1年生の頃に2年生以降のために15人程度のゼミみたいな授業がありました。
その一番最初の授業の時に僕が唯一その時点でできてた友達が、

あの〜さんってTwitterでフォローしてたこの人だよね
といってきました。
もちろん僕の友達もTwitter上でその人と仲良くなっていたわけではなく、ただフォローして面識があっただけでした。
そのためしょっぱなからそれ以上仲良くなるということもありませんでしたが、それでも認識があるのはやはり強いです。
なのでSNS上で仲良くならずも多少なりとも繋がってさえいれば、認識はされやすく最初に話しかけやすかったりします。
もちろんより活発に動いてる人は

Twitterでめっちゃ動いてるあいつに会ってみよう
などと言ってる人もいました。
こういう風に何かしらの面識ができるので事前にSNSを活用することは効果的です。
3、同じ趣味を持つ人と繋がり、サークル仲間にも
SNS上でなら同じ学部内でも、同じ趣味を持つ人と簡単に繋がれます。
そうすると自然と同じサークルや部活に入ろうとしてる人とも繋がりやすくなります。
サークルや部活に初めて見学に行く時などは一人だと中々不安で勇気のいるものです。
しかしSNS上で繋がっておけば一緒に行くこともできます。
これは本当に隣に人がいるのといないのとでは心強さが全然違います。
なので何かのサークルに入ろうと決めてる方はぜひ、繋がっておくことをお勧めします。
先ほども話したようにSNSならプロフィール欄をみればだいたい趣味がわかるため、そこから自分が入ろうとしてるサークルに興味がありそうな人にDMをしてみるといいでしょう。
・SNSを使うのが嫌なら大学主催の交流会に行けばOK

ここまでSNSを使うことがいかに大切かお話ししてきましたが、それでも

SNS上でやり取りするのかめんどくだくて嫌いだ
という方は少なくはないと思いますし、実際僕がそうでした。
ではその方はどうすればいいのか、ただ友達ができずに苦しい思いをするだけなのかというと違います。
実際僕はSNSは使いませんでしたが、気の許せる友達が数人できました。
その方法は大学主催の交流会に参加することです。
これだけではありません。他にもまとめると、
1、大学主催の新入生交流会
2、サークルの説明会
3、1年のゼミもどきの授業をとる
上の二つは特に大切でそこである程度自分と波長の合う友達を探しておきましょう。
そしていざ履修する時にその友達とLINEをして同じゼミのような十数人の授業をとるとより仲良くなれます。
僕の大学では前期でも後期でもゼミほど厳しくはない、ゼミもどきみたいな授業がありました。
そこでより仲を深めることができたのです。
ちなみにその時の友達とは、
新入生交流会で初めて出会い→サークルの説明会に一緒に参加し→ゼミもどきの授業は別だが同じ時間なので授業後に会って一緒に帰る
この流れで仲良くなっていきました。
ちなみにゼミもどきの授業の時に他にも気の合う友達を見つけ、3人というちょうどいいグループができました。
こういう風に友達を作るための発端として交流会に参加することはSNSを使わない場合はとても大切になってきます。
・使うならTwitterで始めてからのLINE&インスタの流れが最強

ここからは
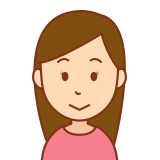
確かにSNSを使うのは友達作りで大事だと分かったけど、どのSNSをどうやって使えばいいの?
という悩みを解消していこうと思います。
ではどのSNSが良いのか表題にも書いていますが、
この流れが正直最強です。
では理由をお話ししていきます。
✔️始まりはTwitterがいい理由
なぜ最初はTwitterがいいのかというのはおそらくなんとなくわかると思いますが、Twitterでしか知らない人と繋がる方法がないからです。
インスタは画像を載せないとダメで繋がるのには圧倒的に向いてないですし、LINEはそもそも不可能です。
そこから消去法的考えてもTwitterしかないですし、タグをつけることで見つけやすくなるという利点もあります。
✔️そこからLINEやインスタに流れていく理由
ではそのままTwitterでいいじゃないかと思うかもしれませんがそうもいきません。
理由は学部のグループラインがあった場合にそこには同じ人間が集まるため便利ですし、個人で話す場合もDMよりもLINEの方がわかりやすいからです。
また最近は大学生くらいだとTwitterよりもインスタをより高頻度で使う人の方が圧倒的に多いです。
ですからTwitterをフォローしてるだけではあまり情報が得られず、インスタの方がどんな人なのかストーリーなどから把握しやすいです。
・効果的なTwitter&LINE、インスタの使い方と注意すべき点

ではこれらをどのようにして活用していけばいいのかという話に入っていきます。
まずはTwitterからお話ししていきます。
1、Twitterの使い方と注意すべき点
✔️使い方
Twitterはとにかく同じ大学、同じ学部の人と繋がるための最初の門となります。
ですから一度#○○大に合格しました。や#春から○○大、というハッシュタグをつけて、これから同じ大学、同じ学部の方よろしくお願いします。
とツイートするといいでしょう。
こうすることで同じ大学の人が見つけてくれてフォローしDMをしてきてくれたり、学部のLINEグループに招待してくれます。
そしてフォローしてきてくれた人の中から自分と同じ趣味を持ってそうな人にDMを送ったり、グループから個人LINEを追加して挨拶をするといいでしょう。
そして

こういうサークルに興味あるんだけどもし○○さんも興味あったら一緒に見学に行かない?
と送るといいんじゃないでしょうか。
✔️注意点
これは最後にもお話しするのですが、#春から○○大というツイートをすると、変な勧誘が来る可能性があります。
例えばサークルの勧誘のDMが来たり、それならまだいいですが、カルト集団という危険な集団が大学生を装って勧誘してくる可能性もあります。
これは本当に危険で大学側でも注意する旨の発信をしてるほどです。
そのためもしDMが来た場合は必ず相手のプロフィールやツイート内容を確認することで、本当に同期の学生か確認してから返信をしましょう。
また返信をしてからも怪しい様子がないか気にするということも大切です。
今時カルト集団でも本物の学生に見えるように細工したり、彼らは勧誘のプロなので「引っかからないだろう」と侮っていると後で本当に痛い目を見ます。
2、LINEの効果的な使い方と注意点
✔️使い方
LINEは先ほども話したように同じサークルの見学に行かないか誘ったりするのに効果的だったりします。
なのでとりあえず学部のグループLINEには参加しましょう。
そうすることで様々な情報(履修に関してやサークルに関して)が得られますし、同じサークルに入る人を求めてる人もいたりと何かと便利です。
✔️注意点
ただ個人のLINEを追加した時にいきなりこのサークルに興味はあるか聞くと、勧誘みたいになってしまい不審ですし、相手も気分が良くありません。
そのためまず最初は名乗って自分もサークルに興味ある旨を述べてから、誘ってみるといいでしょう。
3、インスタグラムの使い方と注意点
✔️使い方
インスタ に関しては正直そこまで重要性はないです。
やらなくてもどっちでもいいですが、やった方がよりどんな人かわかりやすいでしょう。
ストーリーなどをみることでこの人はこういう趣味があるんだなとか、しっかりした人かそうでないかの見分けもつきます。
また初めて直接会ったときに話題にすることもできます。
✔️注意点
注意点もそこまでありませんが、強いていうならあまり変なストーリーはあげない方がいいでしょう。
なぜなら既に見知っている友達なら全然構わないですが、知らない人が見るとストーリーがその人の全てとなり、それだけでどんな人か判断されてしまうからです。
おそらくSNSを使うか迷ってるような人はそんな変なもの投稿したりはしないと思いますが、念のためお伝えしておきます。
・#春から○○大ツイートについて

このツイートは毎年受験が終わるとTwitterにたくさん流れてくるのですが、賛否両論あります。

わざわざ自分の大学を自慢する必要がないだろう
とかです。
ですがこれに関しては少し的外れな批判だと思っていて、このツイートをするのは同じ大学の人と繋がるためだからです。
その上で同じ大学の同じ学部に合格した人が最も見つけやすいツイートがこれだっただけであり、合理性を追求した結果です。
しかし危険性があるという批判は正しいです。
どこかの大学がこのツイートはカルト集団からの勧誘もあるため十分注意するように述べたほどです。
ですからこのツイートは確かに合理的でわかりやすいですが、十分そこには注意するようにしましょう。
ただこのツイートをしない限りSNS上では繋がれないというのも事実です。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
#春から○○大をしなかった者の末路。グループに招待はされないが交流会に参加すればOK
もしくは自らこのツイートをしてる人をフォローしDMを送ることですが、それは少し面倒っちゃ面倒ですよね〜。
・まとめ:SNSを活用することはこのご時世非常に大切

では最後に今回の内容をまとめると
1、SNSを使うと情報収集や大学の友達作りのきっかけとなる点で超大切。
2、使うならTwitterからそしてLINEやインスタに移行
3、ただしTwitterにはカルト集団からの勧誘という危険もあるため注意が必要!
この3点が非常に大切な内容となっています。
今SNSを使っていこうか迷ってる方はぜひこれらの内容を踏まえた上で考えてもらえればと思います。
では今回はこれで終わります。
最後まで閲覧いただきありがとうございました。