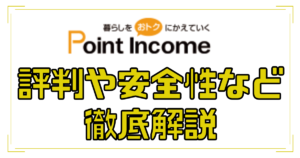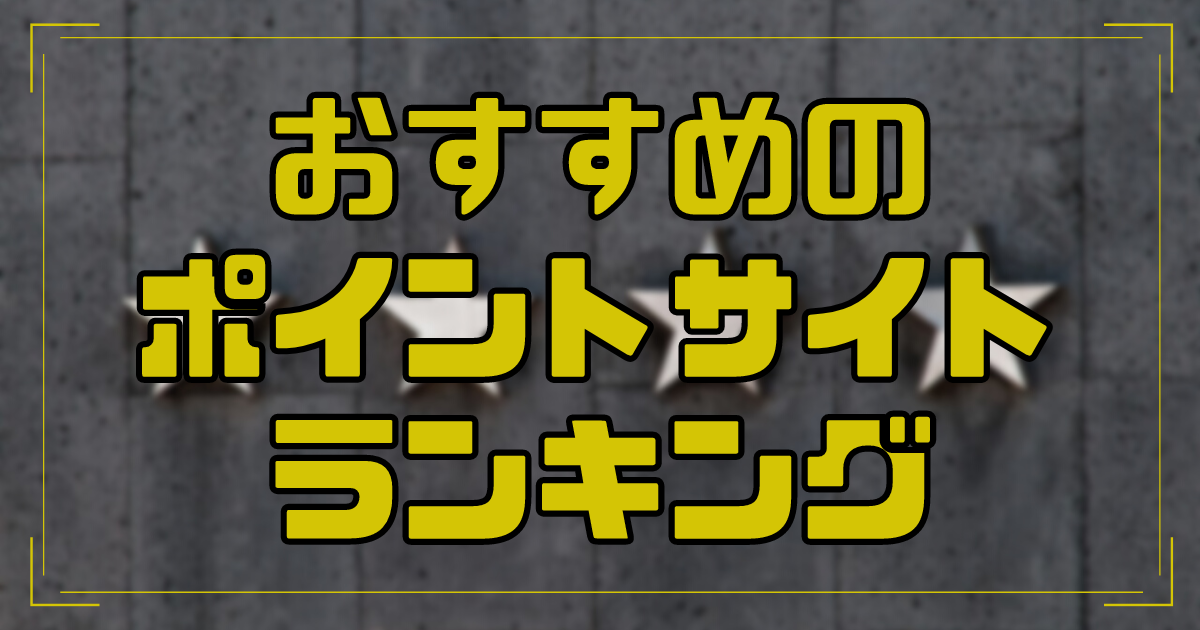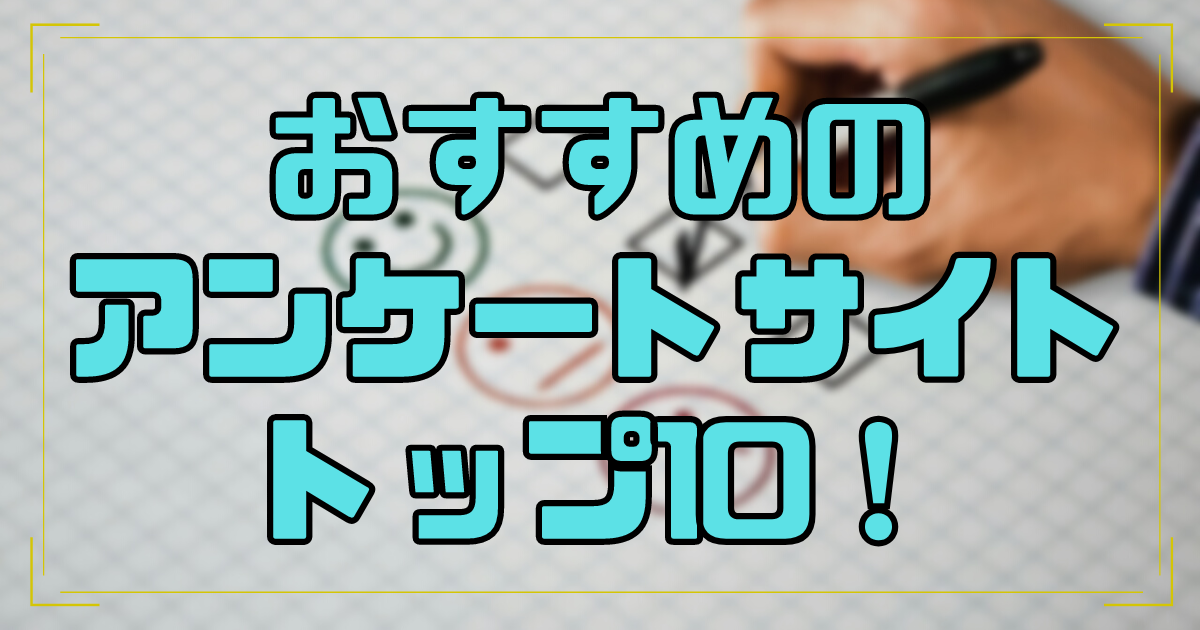自分は計画立てずに勉強するタイプだけどそれでも受験は大丈夫?
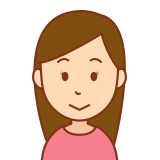
計画なしでもうまく勉強できる人は良くない?
今回はこういった疑問を解消します。
✅内容は
2、計画を立てなくても良いんじゃない?立てないメリットは?
3、めんどくさい人はシンプルな計画だけ立てればOK
4、何事も1度試して合うか確認するのが大切
です。
正直いうと僕も具体的な計画を立てても遂行できないため、あまり詳しすぎるものは作らないようにしてます。
ですから計画を立てない人の気持ちも考えた上で話していくので参考にしてみてください。
目次
・勉強計画を立てないデメリットとは?

では早速結論から述べたいのですが、流石に全く何も考えないというのはダメですし、実際計画を立てないという人も大まかには頭の中で考えてると思います。
ではよく計画を立てろと言われるが立てないとどんなデメリットがあるのか3つ紹介します。
2、多少の強制力がないと楽な方に逃げてしまう
3、何をしてるのわからなくなる
これだけでは分かりにくいと思うので、それぞれ詳しく話していきます。
1、毎日の何をやろうか考える時間とエネルギーが無駄
まず一つ目ですが、毎日のタスクを決めておくと朝から勉強するときに計画通りに遂行するだけなので、余計なことに頭を使わずにすみ楽です。
しかし計画がないと昨日は数学をやったから今日は英語を重点的に云々、いろいろと考えないといけないので少し疲れます。

計画を立てるのに時間がかかるから一緒じゃないか
と思うかも知れませんが、計画なんて大体でいいので数十分で立てれますし、その日のエネルギーを使うだけです。
毎日毎日悩んでいるとそれが重なって時間も結構取りますし、いちいち考えるのがめんどくさくないですか?
これが僕にとっては一番大きなデメリットです。
2、多少の強制力がないと楽な方に逃げてしまう
これは計画というある程度自分を縛ってくれるようなものがないと、楽な方に逃げてしまうということです。
より具体的にいうと、計画で毎日英文法書を30ページ進めると決めていればそれをやらざるを得ません。
しかし決めていないと20ページ終わった時点で今日はもういっかとなってしまったりします。
これの理由としては、そもそも毎日どれくらい進めればいいのか決まっていないことによって、もし前日が10ページしか進まなかったのなら20ページでも多く感じるという現象が起こるからです。
これは自分が今日頑張ったかどうかが昨日とか数日前とかの自分としか比べられないため楽な方に逃げてることに気づけないからです。
そこで計画のような基準があると楽な方に逃げそうになってもこれだけは頑張らないととなります。
また実際に逃げた場合は計画に遅れが出て罪悪感に苛まれ、勉強を頑張るようになる可能性もあります。
その点計画がないと罪悪感すら生まれないため、より勉強しようという活力が生まれないのです。
3、何をしているのか分からなくなる
計画はいわば勉強の地図なので、それがないと自分が今どこにいるのか、どこに向かっているのか分からなくなります。
例えば英語なら今文法を勉強してるとして、計画がないと文法が終わった後にどんな段階があるのか分からず、今どれくらい受験勉強のうち進んできてるのか把握できません。

計画を立てていればこの先に英文解釈があって長文読解があって、さらにその先に英作文とか英文和訳などがある
とぱっと分かります。
これが分からないとモチベーションもなかなか上がりませんし、効率的な勉強はできないです。
・計画を立てなくても良いんじゃない?立てないメリットは?

それでもやっぱりめんどくさいからとか、立てても崩れるだけだから立てたくないという人はいるでしょう。
立てないメリットはどんなことがあるのか見ていきましょう。
1、計画を立てる時間の省略
2、めんどくさいことを考えずに済む
ではそれぞれ説明していきます。
1、計画を立てる時間の省略
計画を立てようとするとやはり時間はかかってしまいます。
それも定期的に見直すとなると、定期的に時間を食うでしょう。
それをせずに済むというのは確かにメリットではあります。
ただし計画を立てる時間を考慮したとして、計画を立てた方が効率よくできることを考えたらどちらがいいのかは怪しいところではありますが。
2、めんどくさいことを考えずに済む
これは計画を立てるのもそうですが、毎日今日はノルマを達成できたかとか、できなくてショックを受けることもありません。
そんな風に自己嫌悪もせずに、面倒なことは考えずに済むでしょう。

ただその代わり毎回何を勉強しようか考えないといけないので、それそれで面倒ではないでしょうか?
・めんどくさい人はシンプルな計画だけ立てればOK
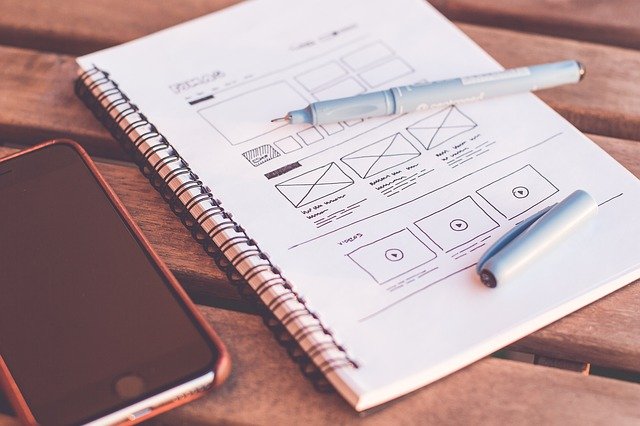
ここまでで計画を立てないことのデメリットとメリットはわかりましたが、ではそれらを踏まえてどうすればいいのか。
結論を先にお話しすると、シンプルな計画だけ立てるといいでしょう。
理由は細かい計画を立てるのは時間がかかりますし、面倒だからです。
それに崩れる可能性も高くなるのでそこまで綿密に立てる必要はありません。
ではシンプルな計画とはどういうものでどう立てるのかポイントを3つ紹介します。
1、月単位の計画だけ立てる
2、できるならそこから1日のタスクを割り出す
3、キツキツにその計画を守る必要はなし
ではそれぞれ解説していきます。
・月単位の計画だけ立てる
細かい日単位の計画ではなく、月単位の計画だけを立てるようにすればいいです。

例えば今月と来月で英文法は終わらせて、その次の月から長文の勉強を始めるみたいな大まかな感じです。
こういう風に月単位であれば数分で計画を立てれますし、月の計画がわかれば1日にどれくらい勉強すればいいのかもなんとなく分かってきます。
いちいちこの日はこれをしてと考える必要もなくやるべきことが把握できるのです。
これをさらに明日の何時からは何をやってとかにするから面倒なのであって、大まかな指針だけあれば大丈夫でしょう。
2、できるならそこから1日のタスクを割り出す
もし月単位の計画を立ててみてまだ余裕がありそうなら1日に何をどれくらいやればいいのかだけ割り出しておくと尚いいです。
それくらいなら月単位の計画を30で割ればいいだけなので一瞬で出せます。
そうするとそれをひたすら続けて勉強し続けるだけでいいのでとても楽です。
それに何時にこれをやるというよりは、昼ごはんの後に数学の問題を5問解くみたいな感じで何かの行動の後にそのタスクを割り振るとよりいいです。
時間だとサボってしまいますが、これなら行動が勉強のトリガーとなってその行動に続けて勉強を行えるからです。
詳しくはこちらを↓
勉強を習慣化するだけで受験は勝ち組です。[理由]マイナスの感情がなくなるから。
3、キツキツに計画を守る必要なし
最後のポイントとして立てた月単位の計画をキツキツに守る必要はありません。
もちろん細かい計画を立てられる人であれば、計画からずれるたびに修正すればいいです。
しかしそれが面倒だから今回のようにシンプルなものにしたわけで、その場合修正なんてしてたら面倒でしょう。
なので計画を必死に守ろうとする必要はなく、ある程度の指針としておいといて後は多少自由にやってもいいでしょう。

もちろん全く計画通りにしないと立て意味がないですが、多少は構いません。
計画を立てずに勉強してきた人はそちらの方がうまくいく可能性もありますし。
・1度試して合うか確認するのが大切
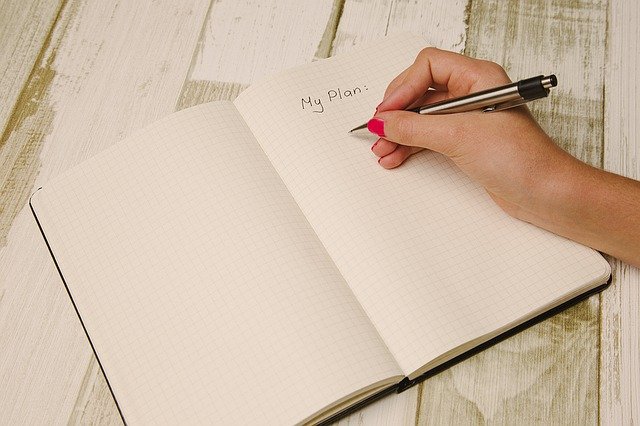
まとめると結局自分に合うやり方でないと絶対に続きません。
ですから必ずしもここで紹介したものが合うとは限りませんし、無理矢理やると逆効果になってしまうかもしれません。
よく世間的には計画を立てないといけないとか言われますが、それは自分がそうだっただけでそれを人に押し付けてるに過ぎません。
それに悪影響を受けないためにも一度実際に自分で試してみて合うか確認してみるということが大切です。

ただ計画を立てないことのデメリットがあることは確かなので、そこはいろいろ試して自分にあう計画の立て方を追求するべきです。
ぜひトライアルアンドエラーをしてみましょう。
最後まで閲覧ありがとうございました。