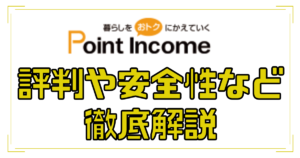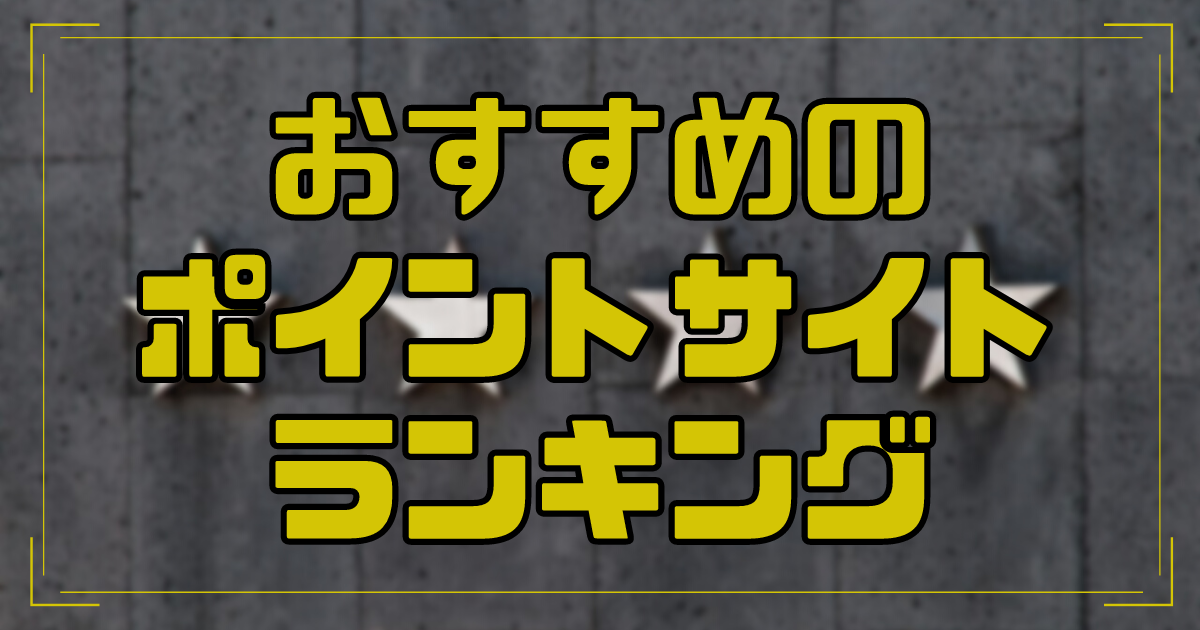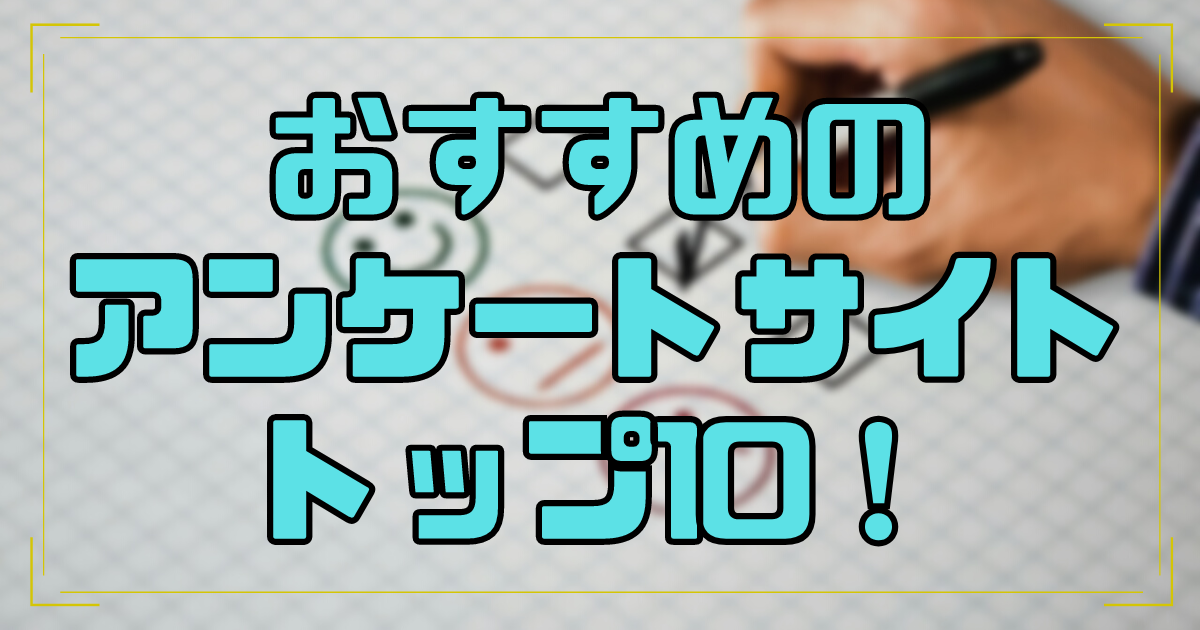過去問をいつから解けば良いのか分からなくて困っている
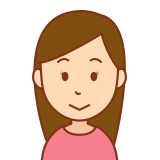
過去問の使い方やどれくらい解けばいいかも知りたい
今回はこういった過去問に関する悩みを出来るだけ多く解消します。
内容は
・大学受験の過去問はいつから使う?
・どれくらい解くのがベスト?
・最も自分の力になる使い方は?
です。
実際に過去問を20年分ほど使っていた経験をもとに話していきます。
過去問に関する必要な知識はここでほぼ網羅してるのでぜひ参考にしてください。
目次
・大学受験の過去問はいつから使う?

早速いつから使うのかですが、大学入試共通テストになってもセンター試験の過去問は使うべきなので、センターの過去問と各大学の過去問に分けて話します。
センター過去問は基本的に12月〜1月に解きまくるのが前提で、苦手な科目は11月から解く感じです。
大学の過去問は共通テスト終わってからは解きまくることが前提なのと、10月か11月の間に少し解いておくのも大切です。
ではそれぞれ解説していきます。
・共通テスト対策としてのセンター過去問
これは先ほども話したように、12月は基本的に解きまくるしかないです。
試験に馴らすのもそうですし、共通テストに必要な細かい知識をつけていくためでもあります。
そして11月に関しては僕は苦手な科目、もしくはもう共通テストに必要な知識は身についたと思う科目は解くのをお勧めします。
なぜなら苦手な科目は11月の時点で得意にできるかというと、それは無理です。
それに苦手と分かっているならそれまでに色々対策はやってきていると思うのですがそれでも伸びていないなら、過去問という実践の場で1点でも多く取る方法を見つけるべきだからです。
僕は国語がとても苦手だったので、早めから解いていました。
でもそのおかげで試験でどう解くべきかが、マーク式に関しては身についたので、センターの本番ではしっかり点が取れました。
後は数学も青チャートは散々解きまくっていて知識は確実についていたので11月から始めました。
英語に関しては大得意でどうやっても180点を切る気がしなかったので、過去問はそもそもそんなに解きませんでした。
社会と理科の科目は知識が全然ついてなかったので、12月の中頃から解き始めました。
まとめると、苦手科目や知識はもう結構ついてるから実践が欲しい科目は11月から、知識がまだ足りないか得意な科目は12月からでいいでしょう。
ただし苦手科目でも知識が無いせいで苦手なだけならそれは知識をつけてから解くべきです。
僕の場合は国語という知識云々じゃ無いものだったから早くから実践に移行しただけですので。
・各大学の過去問
これも先ほど話しましたが、基本的には共通テストが終わったら志望校の大学は解きまくります。
ただし10月から11月にかけても多少は志望校の過去問は解いておくべきかと思います。
やはり10月11月の間にある程度2時試験の筆記の対策はしておかないと、共通テストが終わっていきなり筆記に移るのは大変だからです。
その対策をどうやればいいのかを知るためには過去問を少し解いておかないといけないです。
志望校以外の併願の大学の過去問は、僕の場合は試験数日前に1〜2年分解くといった感じでした。
あまり志望校の勉強に負荷をかけるといけないので、もし学力的に余裕があるなら本当に1か2年分だけでいいでしょう。
逆に第1志望でないのに、自分の学力でギリギリのところの場合でも多くても3年分に留めておくべきです。
僕の場合は10月11月に3年分ほど志望校の阪大の過去問を解いて、センターが終わった後はひたすら阪大の過去問を解きました。
そして併願は同志社の1つの学部の全学部と個別の二つを受けたのですが、両者の試験内容にあまり違いはなかったため、全学部の2日前ぐらいに1年分を解いただけで、それ以外は解いてません。
ではまとめると、第1志望の大学の過去問は10月か11月に少し解いておくのと、共通テストが終わったら解きまくる。
併願の大学は試験数日前に1〜2年分を解くことがお勧めです。
ただしこれもセンターの過去問と同じで、知識があまりついてない科目の場合は、10月11月で実践に行く前にまずは知識をしっかりつけましょう。
知識がある程度ついていて、それを実践でどう活用するかを練習する必要がある科目だけは、10月や11月から時始めると伸びはいいです。
・どれくらい解くのがベスト?
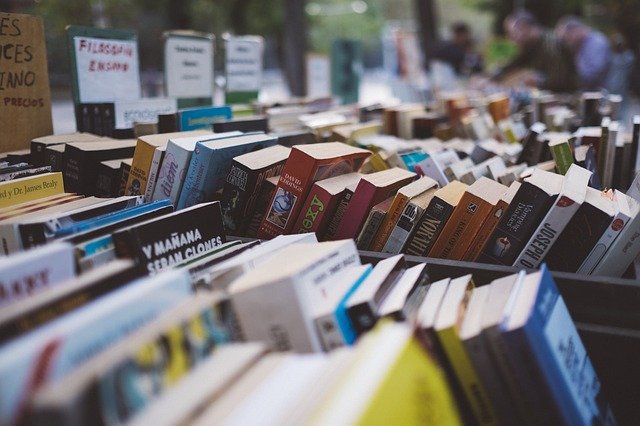
これは非常に簡単で、共通テスト対策としてのセンター試験の過去問は、苦手科目に関してはほぼ全部です。
得意な科目に関してはその程度にもよりますが、180点切る気がしないなら1〜5年分ほどでいいでしょう。
それ以外なら5〜10年分でしょう。
古すぎる過去問を解く意味はあるのかと思うかもしれませんが、それは後の使い方のところでも話しますが、共通テストの知識をつけるためには使えます。
そして第1志望の大学の過去問も同じく全て解きます。
そう例外は先ほども話したように1〜2年もしくは3年分くらいでいいでしょう。
僕の例を出すと、センターの数学の過去問はほぼ全部、但し古い方から5年分ほどは知識をつけるためなので、試験問題としてではなく練習問題として使いました。
国語はもちろん全て、英語は5年分くらいです。
理科の基礎科目は5年分で、社会科目も5年分でした。
志望校はもちろん全て解きました。
・最も自分の力になる使い方は?
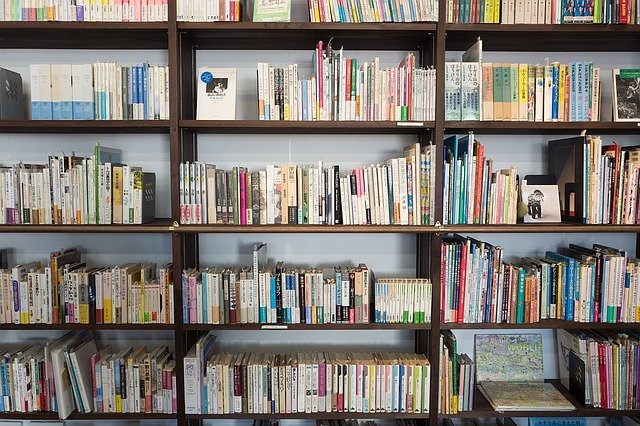
そもそも過去問の使い方のポイントを紹介していきたいと思います。
最後には各科目の過去問を実際にどう使っていたのか使用例を紹介するのでそちらも参考にしてもらえればと思います。
ポイントは3つです。
1、原則は時間を測って解くようにする
2、答え合わせよりも考え方を確認し分析する
3、間違えた問題は頭に叩き込む
それぞれ解説していきます。
1、原則は時間を測って解くようにする
まず1つ目は原則必ず時間を測って解くようにしましょう。
試験における大きな敵は問題の難しさもありますが、時間との戦いもです。
ですから練習と言って時間を測らずに解いても50%の効果しか得られません。
確かに最初の頃は時間を測ったところでそこに収まらないから測る意味ないと思うかもしれません。
しかし時間を測らずに解いて、自分の解くスピードを徐々に上げて時間内に収めるよりも、最初から時間内で解くようにして、徐々に溶ける量を増やしていく方がいいです。
また時間内にできなかったところは点数に入れないつもりで、解いても構いません。
とにかく時間制限を設けることで時間内に解ける量を増やしていくことが大切です。
2、答え合わせよりも考え方を確認し分析する
問題を時終わった後は答えがあってるかの確認も大事ですが、それよりも考え方があっていたのかをしっかり確認してください。
そして自分の答えがなぜこうなったのかと、答えに書いてる考え方があっているのか、間違っているならなぜ自分は間違えてしまったのか考えます。
そして同じ間違いをしないためにはどいうことに気をつけたらいいのかを考えるようにするのです。
こうやって分析をすることで、力は確実に伸びていきます。
逆に答え合わせしかしないとか、解説の考え方を見るだけで自分と比較しないとかではなかなか伸びないでしょう。
3、間違えた問題は頭に叩き込む
前の分析のところでは間違えた問題と似た形式の問題が出た時に間違えないようにするものです。
しかし全く同じような問題が出た時(例えば数字だけが違うとか、同じ文法事項とか)にまた間違えないように、1度間違えたものは徹底的に頭に叩き込みます。
全く同じ形式の問題では2度も間違えてはいけません。
特に共通テストとかだとそこまで深い内容は出ないので、それまでのセンター試験と同じような問題ばかりが出ます。
ですから1度間違えた問題は2度と絶対に間違えないという意気込みでまる覚えしてしまってください。
もちろん答えにたどり着くための考え方をです。
・英数国それぞれの過去問の使い方の例
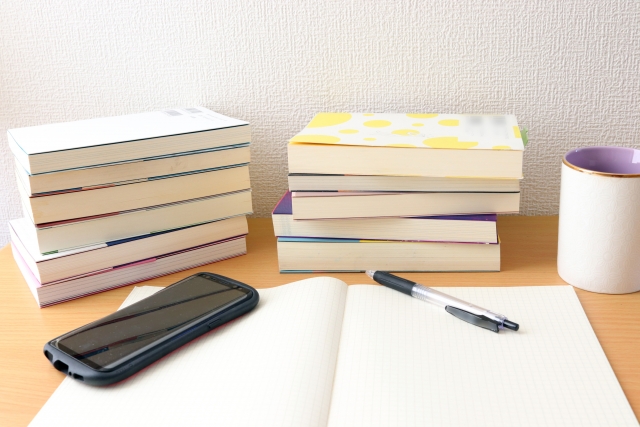
では最後に国語と数学と英語に関してだけどう過去問を使ったか紹介します。
では最初は国語からいきます。
・国語
国語はとにかく時間を測っていかにその時間内でできるだけ高い特典を取るかを気にしてました。
まずセンターの過去問は20年前のものでもそこまで大きく変わってるというものではなかったので、とりあえず全て時間を測って解くというのを繰り返しました。
ですから何か特別変わったような使い方はしてません。
・数学
数学が少し違う使い方をしていて、20年前のものとかになると僕が受験する頃とは数1などの範囲すら違いました。
ですから古い方から5年分は各単元を一気に解いていくという手法を使ってました。
もちろん一応時間は測ってやりますが、二次方程式の範囲ならそれを5年分一気にやる感じです。
そうやって各単元の知識を詰め込んでいくのです。
残りの15年は直近3年分だけセンター直前に残して、12月から解いていきました。
・英語
英語に関しては得意だったので、模試の前日に感覚を取り戻すために1年分解くことが多かったです。
そして12月には1週間に1つか2つ解くぐらいでした。
ただそこで間違えた文法などは絶対に頭に入れてました。
そんな感じです。
最後まで閲覧ありがとうございました。