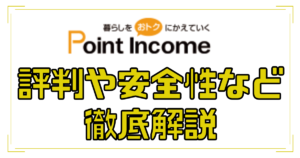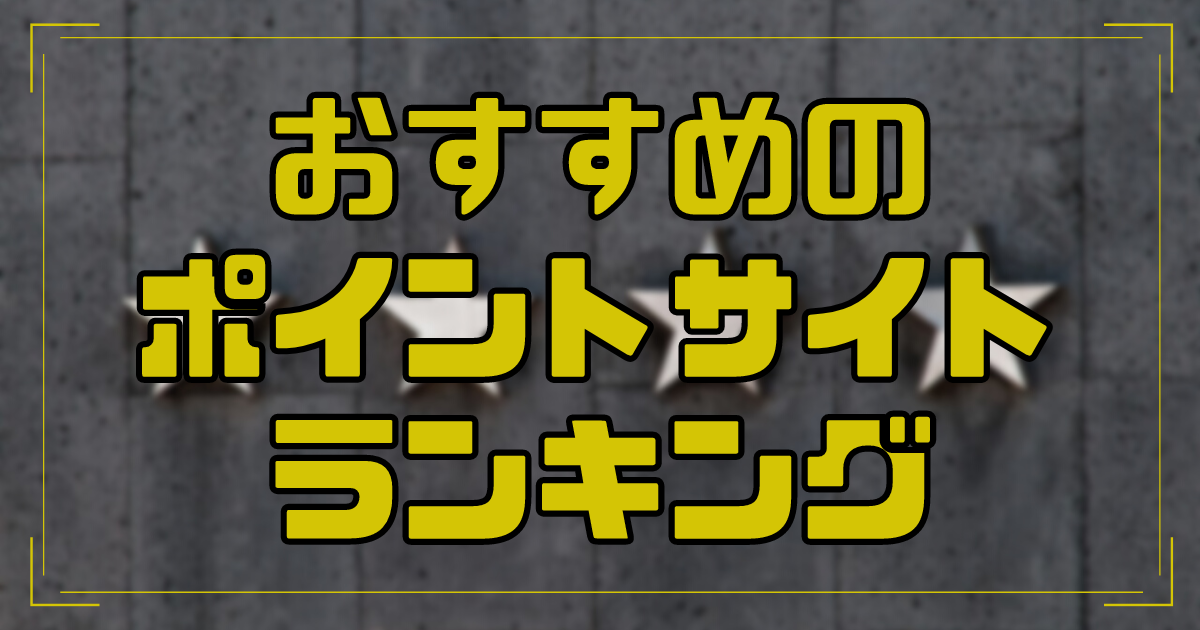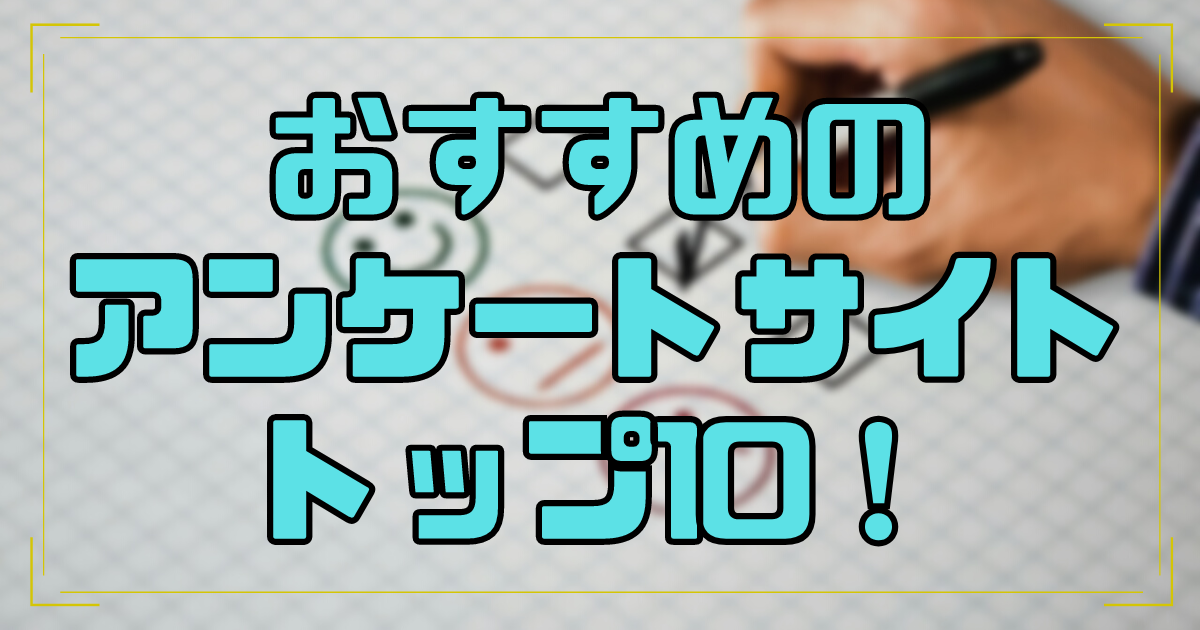暗記科目は朝と夜どっちにやるのが効率がいい?
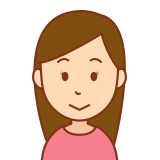
朝はこの勉強をした方がいいとかってあるの?

朝方と夜型どっちの方がいいの?
内容は
・
目次
・勉強は朝と夜で適した科目が違う!?

結論から言うと朝と夜では適した科目は違います。
午前中は数学や物理、そして一部国語や英語などの思考力が問われる科目が適しており、午後は暗記科目中心で午前中にできなかった科目をする、というのがおすすめです。
この行う科目を変えるだけで集中力や、効率というのは格段に違うので気にするべきです。
・午前中は思考力の必要な科目(数学や現代文読解)
午前中にすべき勉強は数学だったり、国語の現代文だったり、特に思考力が必要な科目です。
社会科目はもちろん暗記なので塾考はしませんし、英語なんかも英語を読むのであって、国語よりも単語や文法を覚えてるかなどの記憶要素が大きいです。
もちろん感じ方は人それぞれで、僕は英語が得意だったからそういうのかもしれません。
ですから午前中は数学や現代文の読解、もしくは物理などの考えないといけない科目を勉強しましょう。
基本的にはこの考え方なのですが、もし苦手で苦手でしょうがない科目がある場合は午前中に行うのも一つの手です。
やはり可能ならば特に数学などのとても頭を使う科目をすべきですが、苦手科目というのは苦手というだけでやる気が出なかったり、結構体力を使いますよね。
それに苦手なものを後に残しておくと面倒ですし、結局もう今日は疲れたから苦手科目をやる体力はない、という風にやらなくなってしまいます。
ですから相当な苦手科目があるなら、午前中の元気なうちに苦手科目の勉強をしておきましょう。
ただ暗記ができていないからと言って暗記科目を午前中のうちにやるのはやめましょう。
暗記なんていつでもできるので。
ですからここでいう苦手科目というのは国数英に限られということに注意しておきましょう。
実際に僕も国語が相当苦手だったので1日の勉強の始まりは必ず現代文の問題を解くことでした。
それが終わったら午前中の間に数学もやっておくという感じです。
最後に一つだけ例外を紹介しておきます。
それは朝起きてすぐは暗記の復習をした方が良いということです。
暗記の復習をいうのは前日寝る前に暗記をした内容の復習ということです。
なぜそれが良いのかというと、寝てる間に脳はその日の出来事や勉強したことを整理してくれます。
そして朝起きた時にその前日の内容を復習することでその整理してくれた記憶をより強固なものにしてくれるからです。
ですから、朝起きてすぐは例外で前日の暗記の復習などをお勧めします。
・午後〜夕方は記憶と思考の間の科目
午後は午後でも昼過ぎはまだ思考力もそこまで衰えてないと思うので、朝にやり残した塾考を必要とするような勉強や、記憶と思考の間の科目を行いましょう。
間というのは、例えば英語の長文読解だったり、国語の古文読解だったりです。
これらは結構覚えてるかどうかの要素が大きいが、思考もある程度は必要な科目であるため間とします。
苦手科目の勉強も出来るだけ夕方までには終わらしましょう。
それ以降に持ち越すことは危険です。
・夕方〜夜は暗記科目オンリー
そして夜ですが、夜は完全に暗記科目一択です。
夜に集中して思考することはなかなか大変なことです。
やっぱり眠たかったりとか、眠たくなくても1日の終わりは疲れているため集中できないです。
ですから夜は暗記科目に全力を注ぎましょう。
そして寝る前に数十分集中的な暗記をして次の日の起床後に復習をすることで、より強固な記憶を身に付けましょう。
・どうして朝と夜で適した科目は違うのか
簡単にいうと、朝と夜で人間の脳の働きや体の調子が違うからです。
まず朝ですが、朝起きた時は皆さんどうですか?
もちろん目が覚めてすぐはまだ眠たくて二度寝したかったり、置きたくないと感じることもあります。
しかし、起きてからある程度時間が経てば朝は基本的には元気なはずです。
これもしっかりと睡眠をとってればの話ですが。
だから朝はエネルギーの使う科目が適しているというわけです。
逆に午後は少し疲れが見え始めるため、暗記などのあまりエネルギーを使わない科目が適しています。
特に夕方以降はそう言えるでしょう。
これは単純な話に聞こえるかもしれません。そんなの当たり前だろうと。
しかしではそのことを意識して今まで勉強してきましたか?
闇雲に国語の勉強が終わって、次何しようかなーと場当たり的に勉強することを決めていませんか?
そいう勉強はそもそも何を勉強しようか考える時点でエネルギーを使いますし、効率が悪くなってしまうのでやめましょう。
・実際の1日の勉強例
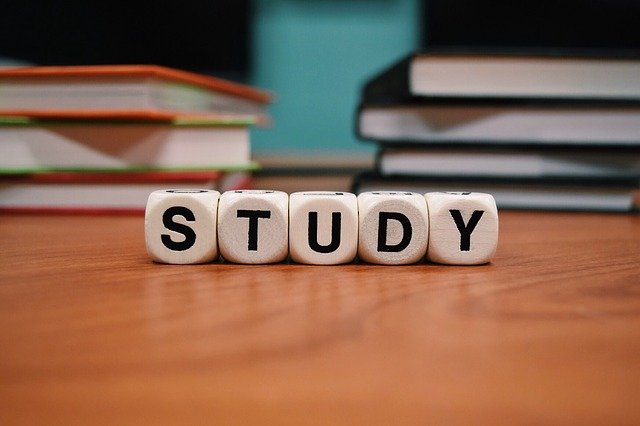
ここでは実際に僕が行なってた1日の勉強例を紹介するので参考にしてみてください。
まず朝6時半とかに起きると前日の夜に行った暗記の復習をするのですが、正直全部できてたかというとそこまで真面目ではなかったので、5分ぐらい思い出すという感じでした。
そして朝ごはんを食べて8時から勉強スタートですが、まずは現代文の文章問題を2問と古文の問題を1問解きます。
これは受験までほぼずっとこのタイミングで行ってました。
なぜなら国語が僕は苦手だったからです。
そうするといつの間にか習慣になってました。
その後に数学の大学の過去問とか問題集でも難し目の問題を3問ぐらい解くか、まだそういう段階でない時でも数学の簡単目な問題を気力が続く限り頑張りました。
これで大体休憩も挟むと、順調に行った時は11時ちょっととかで、調子が悪い時は12時前になることもありました。
ここで基本的に朝の勉強は終わるのですが、もし余力があれば英語の長文をちょっと読んだりします。
そして昼ごはんを食べてからは、僕は体力を回復するために一旦20分くらいの昼寝を挟むことが多いです。
そして起きたら朝の英語の長文の続きを行います。
それで大体2時半〜3時くらいで、4時までは数学のチャートをひたすら頭の中で解いて解法を叩き込んでいくという感じが多かったです。
それ以降は間で30分〜1時間ぐらいのサッカーを挟みつつひたすら暗記科目をする感じでした。
だいたいで話しましたが、ここで書いた時間の感覚通りに勉強できてるかというとそういうわけではなく、結構間に休憩を挟んだりして、勉強時間は7〜8時間ぐらいが常でした。
参考になりましたか?
・結局朝型と夜型どっちが良いの?

じゃあ朝型と夜型どっちが良いのかと言う話をしていきます。
・クロノタイプによりけり
まずクロノタイプとは何かというと、人間の体内の時間的な傾向のことです。
普通人は昼行性なので、昼には活発になり夜には眠たくなると思います。
しかしそれぞれの体内時計は少しづつ違っており、夜の10時になるととても眠たくなる人もいれば12時にならないと眠たくならないと言う人もいます。
そしてこれが勉強のやる気とか集中力とか言ったものにも影響してきます。
クロノタイプには夜型の人もいて、その人は朝や昼よりも夜の方が活発になり勉強に集中できるのです。
ですからクロノタイプによって朝方がいいのか夜型がいいのかは変わってきます。
ここでどっちみち試験は朝からあるのだから朝方の方がいいし、世間一般では朝勉強する方が良いと言われてるため、朝方に矯正すれば良いじゃないかと思う人もいると思います。
しかしこのクロノタイプというのは遺伝子レベルで決まってるものであり、それを変えるのは不可能なんじゃないかという研究結果もあります。
だから勉強するだけの場合は自分のクロノタイプにあったスタイルで勉強すべきなのです。
じゃあ夜型の人は試験はどうすればいいのかということになります。
それは1ヶ月ほど前から朝早くに起きて勉強する練習をしておきましょう。
クロノタイプを変えるとまではいかなくとも、慣れることはできると思います。
それにそれしか対応策はないと思います。
最後に自分のクロノタイプを知る方法を説明します。
・クロノタイプを確かめる方法
クロノタイプは簡単な分類で言うと4つあります。
1つは朝に最も生産的になるタイプ。
2つ目は昼に最も活発になるタイプ。
3つ目は夜に活発になるタイプ。
4つ目が独特で最も活動的なのは夜だが起きてる間は基本的に生産的と言うタイプです。
詳しいことやチェックの仕方はこちらをどうぞ。
自分の体内時計は人と違う?遺伝子によって決定されている、4タイプの属性が分かるクロノタイプ診断|今藤伸之介|note
こちらのサイトはクロノタイプについてとても詳しく書いており参考になります。
そしてクロノタイプなら朝に適した科目も何もないじゃないかと思う人は多いと思います。
しかし人口の50%は朝に活発になるタイプで、15〜20%は昼に活発になるタイプだそうです。
ですから70%の人が序盤で話した、各勉強に適した時間帯というものが当てはまるわけです。
それに結局試験は朝から行われるため、それに慣れさせると言う意味では参考になると思います。
・受験の1〜2ヶ月前以降は朝方に慣れよう
確かに夜型のタイプの人は夜に勉強した方が効率がいいですし、受験が近くない間はそうすべきです。
しかし受験というのは朝早くから始まるものであり、それを変えることはできません。
ですからいくら夜の方が効率がいいとは言え、遅くとも受験1ヶ月前からは朝早くに起きて勉強するようにしましょう。
でないと本番で眠たくて全然集中できないとか、もったいないことになってしまうので。
辛いとは思いますが、仕方のないことなので、うまく順応できるように1ヶ月くらいは期間を持って慣らしましょう。
最後まで閲覧ありがとうございました。